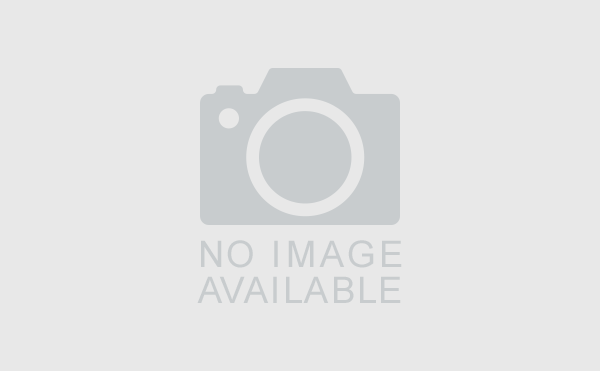| 1 | 総務省「情報通信白書」令和7年版 – 日本の生成AI利用率26.7%、米中に遅れ | 総務省が7月に公開した情報通信白書で、2024年度時点の日本における生成AI(ChatGPT等)個人利用率は26.7%と報告されました。前年の約3倍に急増したものの、米国68.8%、中国81.2%と比べ依然低水準であることが示されています。 | 日本では20代の利用率が44.7%と平均を上回る一方、全年代平均では約4人に1人に留まります。用途は「調べもの」「要約・翻訳」が中心。生成AI開発競争が激化する中、日本の利用の立ち遅れが浮き彫りになりました。白書はこの他、AI活用国別ランキングで日本が9位と低迷し、民間AI投資額でも世界12位と指摘しています。日本がAIで出遅れる背景として、人材不足や企業の慎重姿勢を挙げ、政府は推進策強化を訴えています。 | 本統計は日本社会に警鐘を鳴らすものです。生成AI利用が世界トップクラスの米中と大差がある現状は、将来的な経済競争力やイノベーション創出に影響しかねません。政府が「AIフレンドリー国家」を掲げ各種施策を打ち出す根拠ともなっており、企業経営者や教育現場に対しAI活用促進の必要性を示す重要データです。世代間格差も見られるため、若年層以外へのリテラシー向上策など政策立案にも資する内容となっています。 |
| 2 | 企業の生成AI導入、約4社に1社が実施 – ICT総研調査 | ICT総研が7月2日に発表した調査によると、国内企業で「生成AIを業務利用している」割合は24.4%に上ることが分かりました(2025年調査)。15.0%が本格利用、9.4%がトライアル利用で、導入検討中7.4%、未導入・未検討は約46%でした。 | 調査では「導入予定なし」が46.2%と依然多く、企業姿勢は二極化しています。一方でChatGPTの業務利用率が52.1%でトップ、次いでMicrosoft Copilot 42.3%、Google Gemini 28.5%と主要プラットフォーム系AIが浸透していることも判明しました。利用企業では目的として「業務効率化」「意思決定支援」「創造的業務補助」に高い期待が寄せられ、中小企業や非IT業種でも操作性向上やコスト低下により導入ハードルが下がってきたと分析しています。今後は生成AIが「業務標準の一部」として定着し、幅広い企業でビジネスプロセス再構築に寄与すると予測されています。 | この調査結果から、日本企業の約4分の1が既に何らかの形で生成AIを導入している現状が読み取れ、昨年から急速に普及が進んだことが裏付けられました。しかし半数近くはいまだ慎重であり、費用対効果やセキュリティへの懸念がうかがえます。主要AIサービスの利用率データは、どのプラットフォームがビジネス現場で支持されているかを示し、ITベンダーやユーザー企業の戦略策定に資する指標です。今後、未導入企業が競争上不利にならないよう成功事例の共有やコスト低減策が重要になると考えられ、生成AI市場の成長余地を示す点でも意義深い結果です。 |
| 3 | Z世代の生成AI利用率は約50% – MERY調査、興味の二極化も | Z世代(15~29歳)の約半数が生成AIツールを使用経験ありとするアンケート結果がMERY Z世代研究所から発表されました。2025年7月実施の調査で、49.2%が何らかの生成AIを使ったことがある一方、50.8%は未体験で、非利用者の60%近くは「今後も使いたいツールは特にない」と回答し興味が二極化しています。 | 利用頻度を見ると、生成AIを使ったことがあるZ世代の60%以上が「週1回以上」活用しており、その内14%は「毎日使う」と回答しました。一方「試しただけで継続利用せず」が12%存在し、ライトユーザー層も一部あります。よく使うツールは1位ChatGPT、次いでGoogleのGemini、Microsoft Copilot、Grok(米国OpenAI系のサービス)とテキスト生成系が上位を占めました。Z世代はAI活用に前向きな半面、「AIに頼りすぎず自分の判断もできる人がAIと上手く付き合っている」といった回答も多く、AIを道具としてバランス良く使うことが理想像とされています。 | 若年層における生成AI浸透度が約5割に達したことは、市場として無視できない規模になったことを示します。Z世代は今後の労働市場の中心であり、この世代のAI活用意識は企業の人材戦略や教育方針にも影響します。興味が二極化している点は、今後サービス提供側が使い方を啓蒙しユーザー層拡大を図る余地があることを意味します。高頻度利用者が一定数存在する一方で未経験者も多い現状から、UIの改善や有用性の訴求次第で更なる普及が期待でき、Z世代の動向はAIサービスの方向性を占う上で重要な指標です。 |
| 4 | AI活用の壁は「コスト」が最大 – 導入関心企業の61.4%が課題視 | 7月発表のデジタルダイナミック社アンケートによれば、GPUサーバー活用に前向きな企業のうち61.4%が「導入・運用コストの高さ」を課題に挙げました。Interop Tokyo 2025来場のIT担当者88名を対象に実施された調査で判明したものです。 | 回答者の64.8%は「自社ビジネスでGPUサーバーを活用したい/検討中」と高い関心を示す一方、具体的ハードルとして「コスト高」が突出し、次いで「必要スペックが不明」(33.3%)、「運用人材・ノウハウ不足」(22.8%)が挙がりました。これは生成AIブームで企業がAIインフラに興味を持ちながらも、初期投資や維持費への不安が導入を鈍らせている実態を示しています。専門家は、高性能GPUの自社保有はセキュリティや性能面でメリットがある反面、人材確保やオンプレ運用の負担も大きく、クラウド活用や専門サービスの併用でコスト最適化を図るのが有効と指摘しています。 | 本調査は日本企業のAI導入意向と課題を端的に表しており、特にコスト面への懸念が普及のボトルネックであることが分かります。生成AIやHPC需要が拡大する中、ベンダー側には価格モデルの柔軟化やマネージドサービス提供など解決策が求められるでしょう。政府の補助や共同利用型の計算インフラ整備も、有効な支援策となり得ます。技術的関心は高いものの知見不足も指摘されており、人材育成や情報発信によって企業の不安を解消しAI活用を促進する必要性を示すデータと言えます。 |
| 5 | ChatGPTユーザー、世界で5億人超に – 米国では28%が業務利用 | 米国メディア報道によると、ChatGPTの月間ユーザー数が世界で5億人を突破し、米国では約28%の労働者が業務でChatGPT等のAIツールを利用しているとの調査結果が報じられました。生成AIが一般消費者からビジネスパーソンまで急速に広範囲へ浸透している実態が浮き彫りです。 | これは米調査会社の分析に基づくもので、特にオフィスワーカー層でAIアシスタントの採用が拡大しているとしています。タスクの自動化や文章作成補助など目的は様々ですが、従業員の約3割が日常業務にAIを組み込み始めている割合は驚くべき高さです。米国の技術受容の速さを示す一方、同様の割合に至るには日本ではまだ時間を要すると見られます。なお一般消費者においても、ChatGPT公開から1年あまりでユーザー数が5億人規模に達したのは、インターネットサービス史上類を見ないスピードとも指摘されています。 | このデータは生成AIが単なる流行を超え、日常ツールとして定着しつつあることを示唆します。仕事で3人に1人がAIを使う状況は、生産性や働き方に大きな変化をもたらす可能性があります。日本企業もグローバル競争の中で取り残されないために、AI活用をタブー視せず積極的に取り入れる必要性が増しているといえます。またサービス提供者側にとっても、これだけ大規模なユーザーベースが形成されたことで、AIアプリケーション市場の潜在性が非常に高いことを裏付ける指標です。 |
| 6 | 日本のAI人材需給ギャップ、2040年に最大約326万人不足 – 東大調査 | 東京大学松尾研究室の分析によると、現状のままでは2040年に日本で最大約326万人のAI・デジタル人材が不足する見通しが示されました。無料オンラインAI講座受講者が累計7.5万人を突破したことも発表され、急務となる人材育成への取り組み状況が報告されています。 | この試算は国内のDX推進速度と人口動態を踏まえたもので、AI人材不足は日本経済の成長制約になる可能性があると警鐘を鳴らしています。政府や大学・企業はプログラミング教育やリスキリング施策を強化していますが、需要増に追いつかない懸念があります。一方で松尾研が提供する大規模オンラインAI講座(生成AIの原理や活用法を学ぶ無料コース)には若手社会人や学生を中心に応募が殺到しており、人々の学習意欲の高さもうかがえます。受講者アンケートでは「業務に役立てたい」「転職に活用したい」との声が多く、実践的人材育成が求められている状況です。 | この報告は、日本がAI時代に競争力を維持・向上させる上で人材育成が最大のボトルネックであることを明確に示しました。326万人という不足数は危機的であり、教育改革や企業での継続学習の仕組みづくりなど抜本的対策が必要です。幸い民間主導のオンライン講座など裾野拡大の動きも出ており、今後産学官連携で人材育成を加速することが急務です。日本のDX成否は人材にかかっているとの認識を広める意味で、非常に重要な調査結果と言えます。 |
| 7 | EC消費者のAIチャット活用増加 – 迅速回答が購買後押し | オンライン通販利用者の間で、商品選びや疑問解消にAIチャットを利用するケースが増えています。海外大手ECではAIが商品の比較提案やレビュー分析結果をチャット形式で回答する機能を実装し、消費者の購買判断を支援しています。 | 例えばあるECサイトでは「〇〇な用途におすすめの商品は?」と質問すると、AIが数百万件のレビューを解析しニーズに合う上位3商品を理由付きで提示します。利用者からは「検索より楽」「自分では気付かなかった商品を知れた」など好評で、実際にチャット経由の購入率が向上したとのデータがあります。また返品対応など顧客サポートもAIチャットが担い、24時間即時回答で顧客満足度向上に寄与しています。 | 消費者がAIを身近な相談役として受け入れ始めている兆候であり、小売業のマーケティングやCX(顧客体験)戦略に影響を与えるトレンドです。日本のEC事業者にとっても、利便性向上のためAIチャット導入は競争上避けて通れなくなるでしょう。ユーザー視点ではより適切な商品に出会いやすくなり購買満足度が上がるメリットがあり、企業側には売上拡大とコスト削減の両効果が期待できるため、Win-Winの施策として注目されています。 |

 Add to favorites
Add to favorites