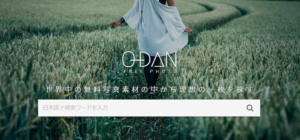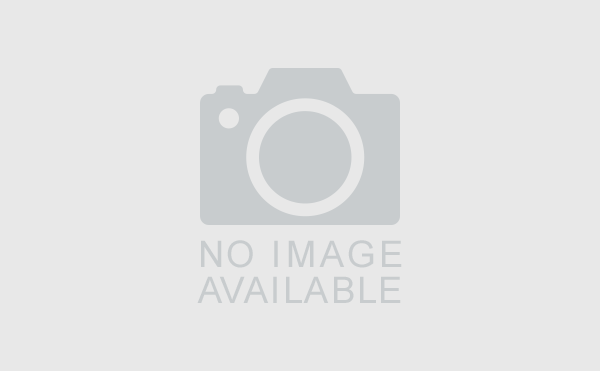| 1 | LINEヤフー、全社員に生成AI活用を義務化 – 3年で生産性2倍目標 | Zホールディングス傘下のLINEヤフーは7月14日、従業員約1.1万人全員に業務での生成AI活用を義務付ける新方針を発表しました。AIを前提とした働き方に移行し、今後3年で業務生産性を2倍に高める大胆な目標を掲げています。 | 同社はまず業務時間の約3割を占める「調査・検索」「資料作成」「会議」からAI活用を導入します。「まずはAIに聞く」「ゼロから資料は作らない」「会議議事録はすべてAI作成」等の具体的ルールを策定し、効率化を徹底する方針です。既に全社員にChatGPT Enterpriseのアカウントを付与し、社内独自ツールや研修で準備を整えています。生成AI活用推進担当者を各部署に配置し、活用事例の社内表彰やアンバサダー制度も導入予定です。社員はAIでアウトライン作成や文章校正を行い、会議はAIで整理・記録して生産的議論に集中するという、新しい働き方への転換を図ります。 | 日本企業として前例のない全社AI活用義務化の試みであり、その成果は他社のDX戦略にも影響を与えます。仮に3年間で生産性2倍という目標を達成すれば、AI導入を躊躇していた企業にも強い成功例となり得ます。一方で社員のリテラシー向上やデータセキュリティ確保など課題も伴いますが、LINEヤフーの挑戦は国内における働き方改革と生成AI活用のモデルケースとして注目度が非常に高く、業界全体の変革を促す可能性があります。 | |
| 2 | ソフトバンク、国内最速AIスーパーコンピュータ構築 – NVIDIA最新GPUを採用 | ソフトバンクはNVIDIA社と提携し、最新GPU「Blackwell」を搭載した日本最高性能級のAIスーパーコンピュータを構築すると発表しました。自社の生成AI開発や提供サービスに活用するほか、国内の大学・企業にも計算基盤を提供予定です。 | 7月下旬のイベントでNVIDIA黄CEOと孫正義社長が登壇し、Blackwell世代の「DGX B200」システムを日本に優先投入する大規模パートナーシップを発表しました。ソフトバンクは既に2000基超のGPUから成る0.7エクサFLOPS級AI基盤を運用中で、今回さらに最新GPUで強化し「世界最大級のAI計算基盤」を目指します。この新スパコンは同社の生成AIサービス開発や5G×AIエッジ領域(自動運転遠隔サポートやロボット制御など)にも応用され、キャリア網の余剰容量でAI推論を同時実行する実証も成功しています。構築したAI計算リソースは国内の研究機関・企業にほぼ無償でトライアル提供する計画で、日本のAIスタートアップ育成も視野に入れています。 | ソフトバンクによる巨額投資のAIインフラ整備は、日本のAI産業競争力を押し上げる起爆剤となります。最新GPUを大量投入した計算環境を国内共有することで、大学やスタートアップが高価なリソースを利用可能となり、イノベーション創出が加速する期待があります。また孫氏が掲げる「全ての人にAIエージェントを」のビジョン実現へ向けた基盤整備と位置付けられ、他国に比べ遅れ気味だった日本のAI開発環境を一気に底上げする重要な戦略と評価できます。 | |
| 3 | 孫正義氏「社員1人に1000のAIエージェント」構想を表明 – SoftBank World 2025 | ソフトバンクの孫正義社長は7月18日のSoftBank World基調講演で、「常時オンのAIエージェントを社員1人当たり1000体持つ」未来像を語りました。AIを“千手観音”のように活用し、人間の能力を千倍に拡張する構想です。 | 孫氏は、かつてのPCやスマホ普及になぞらえ「全ての人にAIエージェントを提供したい」と述べ、24時間稼働する多数のAIが各社員を補佐する世界を描きました。例えば1000個のAIエージェントが知識検索・文章作成・翻訳・スケジュール管理などあらゆるタスクを並行処理し、人は創造的業務に専念できるといいます。これは生成AIとクラウドの発展で現実味を帯びつつあるビジョンであり、孫氏は同社の巨大AI計算基盤を活用して実現を目指す考えです。実際、社内では既に類似のAI活用を試行しており、今後サービス化も視野に入れると示唆しました。 | この構想は企業トップによる大胆なビジョン提示として大きな反響を呼びました。実現すれば人材不足や生産性向上の解決策となり得る一方、AIエージェントの精度・信頼性や人間との役割分担など課題も伴います。それでも孫氏の発言は国内外の経営層にAI活用の可能性を再認識させ、各社が自社の業務に多数のAIを組み込む戦略を検討する契機となりました。日本企業のDX推進において象徴的なビジョンと言え、実現度合いが今後注目されます。 | |
| 4 | アクセンチュア、全社員向けAIエージェントで働き方改革 – 内部チャットボットを高度化 | グローバルコンサル大手のアクセンチュアは、社内でAI活用を加速し全60万人超の従業員に専用AIエージェント「PWPバディ」を展開予定です。既存の社内チャットボット「Randy-san」をGPTベースに強化し、あらゆる社内問い合わせに対応しています。 | 同社は2017年から社内AI活用を進め、2023年にチャットボットを最新GPTモデルにアップグレードした結果、人事・総務・経費精算など月7万件の問い合わせに対応し、2024年4月時点で月間1.1万人が利用、年間20万時間の工数削減を達成しました。今春からは全社員が使える生成AIエージェント「PWPバディ」を導入予定で、社員一人ひとりの業務を支援し働き方を根本的に変革するとしています。「Client Zero」の方針の下、まず自社でAIを徹底活用し得られた知見をクライアント支援に生かす戦略で、AIを“社員のパートナー”と位置付け生産性と付加価値向上を図っています。 | アクセンチュアの事例は、大企業が社内で生成AIを全面展開する先進例として注目されます。膨大な従業員にAIエージェントを行き渡らせることで得られる生産性向上効果は他社のROI算定の参考となり、AI導入の後押しとなるでしょう。同社は自ら実証することで顧客企業への説得力を高めており、業界全体のAI活用を加速させる推進力にもなっています。人員が多い企業ほど定型業務削減のインパクトは大きく、人材不足への対応策としても今後多くの企業が追随する可能性が高い重要なケーススタディです。 | |
| 5 | マニュライフ、社内生成AI導入75%達成 – グローバル金融で業務革新 | カナダ拠点の保険大手マニュライフは今年3月、全世界の従業員の75%以上が生成AIツールを活用中と発表しました。2027年までにAI活用によるROIを3倍に高める目標を掲げており、日本法人マニュライフ生命も含め社内の幅広い業務でAIを本格展開しています。 | 同社では文章作成支援、データ分析の高速化、社内コミュニケーション円滑化、顧客問い合わせ対応準備の効率化など、多岐にわたる業務プロセスに生成AIを組み込んでいます。これにより従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い戦略業務に集中できるようになりました。マニュライフの積極投資と従業員教育により、短期間で社内AI浸透率を大幅に高めた点が特筆されます。金融・保険業界はDXが急務の分野であり、同社の成功は日本を含む他の金融機関にとってもベンチマークとなっています。AIリテラシー向上や経営層の強力なリーダーシップが導入成功の鍵だったと分析されており、導入検討中の企業への示唆に富みます。 | マニュライフの事例は伝統的な金融業における生成AI活用の先駆例であり、その効果が業界全体へ波及する可能性があります。AI導入で業務効率とサービス品質を両立させ、顧客満足度向上にも繋げている点は、規制の多い保険・金融分野でもAIが競争力強化に有効であることを示しました。慎重姿勢が多かった日本の金融機関にも刺激となり、今後国内での生成AI活用拡大の追い風となる重要なケースです。 | |
| 6 | トヨタ子会社ウーブン、生成AIで仮想都市シミュレーター開発 – 街づくりに活用 | トヨタグループのウーブン・バイ・トヨタは、生成AI技術を用いた「CitySim」と呼ぶ100万人規模の仮想都市シミュレーターを構築しました。AIが膨大な交通・人口データから仮想都市を生成し、将来の都市計画やモビリティサービスの検証に役立てます。 | CitySimではAIが自動運転車や歩行者の動きを模擬し、膨大なシナリオで都市の交通流動やエネルギー需要を再現します。トヨタが静岡県に建設中の実証都市「ウーブンシティ」での実験データとも連携し、現実と仮想空間を往還しながら都市モデルを高度化しています。これにより道路設計や渋滞緩和策、新モビリティサービス導入時の効果を事前に評価でき、都市づくりの効率と精度を飛躍的に高める狙いです。生成AIにより複雑な都市環境をリアルタイム生成・解析できる点が革新的で、今後自治体や他企業との協業も視野に入れています。 | 製造業から街づくりまで手掛けるトヨタの先進プロジェクトであり、生成AIの産業応用の幅広さを示す事例です。仮想都市シミュレーターは自治体の都市計画や防災対策にも応用可能であり、国内外で関心を集めています。トヨタのような大企業が先行して技術基盤を築くことで、日本発のスマートシティ関連ソリューションとして輸出産業になる可能性もあります。産官学連携での活用も期待され、社会課題解決にAIを役立てる好例として重要です。 | |

 Add to favorites
Add to favorites